先生方のための科学教室を、2018年11月22日(木)に郡山市立安積第三小学校で行いました。

今回は、理科担当の先生から、6年生で指導する天文教材、特に「月の満ち欠け」の指導が難しい、また、郡山市内で化石採集をできる場所があったら紹介してほしいとの問い合わせをいただき、科学教室を実施することができました。
まず、最初に「月の満ち欠け」の具体的な指導を、以下の4段階に分けてお話しました。
(1)太陽光でできる「陰」と「影」の違い(小3太陽と地面の様子の学習の復習)
(2)「月」と「太陽」を固定し、月の周りを地球が回ったら、月はどう見える?
(3)「地球」と「太陽」を固定し、月が地球を回ったら、月はどう見える?
(4)「鈴カステラ」を楊枝にさして、月の「満ち欠け」を再確認しよう。

先生方からは、次のような感想をいただきました。
・「陰」と「影」を使い分けて指導することが、とても重要であることに気づきました。
・月の周りを地球が回るという模擬実験を実施することで、月の「満ち欠け」の様子を児童一人一人がしっかり確認できること。また、簡単な材料で、しかも、明るい場所でも実験できることは、効果的で準備も楽で非常に良いと思いました。
・ビデオカメラを地球に見立てて行う(3)の実験は、教室を暗くする必要はありますが、モニターに映し出される月の満ち欠けの様子は、説得力があると感じました。また、鈴カステラを児童一人一人が各々持って、「満ち欠け」を再確認できる作業も、大変インパクト?(最後に食べられる)のある実験だと思いました。

「満ち欠け」指導のあとは、郡山市内でとれる化石についてお話をしました。
今年5月に実施した、「地質の日記念 野外講座 郡山で化石をさがそう」で実際に採集した化石をご覧いただきました。化石を発掘した地層は、逢瀬町にある「堀口層」と呼ばれる1200万~1500万年前の海の地層で、さまざまな貝の化石が発掘できます。貝化石が豊富に含まれているので、児童一人一人が化石採集を楽しむことができる事などについてお話をしました。
最後は、「はやぶさ2」の最新情報について、お話しました。
郡山市立安積第三小学校の先生方、そして、この科学教室実施にあたって後押しして下さった校長先生に感謝いたします。本当にありがとうございました。
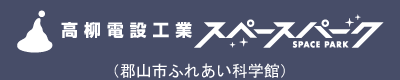





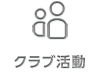
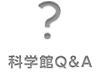
 HOME
HOME




