郡山市ふれあい科学館では2023年9月3日(日)に、公益社団法人日本雪氷学会・日本雪工学会とともに、日本全国から集まった雪や氷の研究者による楽しい実験や工作、展示などを行う「雪氷楽会(せっぴょうらっかい) おもしろ科学体験!雪と氷のふしぎ」を開催しました。
当日は、全部で12のコースを設定して、来館した多くのお客様に雪や氷の科学の楽しさを体験していただきました。
来館者の皆さんからは「楽しかった」という声をたくさんいただくことができました。ご来館いただいたお客様、雪氷楽会に出展いただいた皆様、本当にありがとうございました。

コース1:Dr.ナダレンジャーの自然災害サイエンスショー
Dr.ナダレンジャーが、雪崩、突風、落石、地震を、とっても小さな実験にしました。
本当はこわい災害も小さくすれば楽しいおもちゃになります。おもちゃで遊ぶ感じでいつの間にかお勉強ができるサイエンスショーに、来館者の皆さんは、一部の実験に参加したりもしながら、ご家族揃って楽しく学んでいるようでした。

コース2:3分間の台風疑似体験「ヘラセオン-R」
豪雨や暴風(台風)材を疑似的に体験できるアトラクションです。「時間雨量80mmを超える大雨」や「平均風速30m/sの暴風(台風)」など、モニターの画面に映った来館者の皆さんに災害級の豪雨や暴風におそわれていただきました。
人気コーナーで、繰り返し体験される方もいらっしゃいました。

コース3:帰ってきた北極基地探検
南極に日本の観測基地があることは知られていますが、北極に近いスバールバル諸島にも日本の北極観測基地があります。この場所には様々な国々の観測基地があり、国際観測村として運営され、北極圏の自然環境に関する様々な分野の研究が進められています。
今回はタブレットを使って来館者の皆さんに観測基地を探検したり、基地から見えたオーロラを楽しんでいただきました。

コース4:雪結晶の分類ストラップ
空から降ってくる雪の結晶にはいろいろな形があります。その形から雪の結晶は現在121種類(みぞれや雹なども含みます)に分類されていて、しかも「針」や「星六花」といったように、全ての形に名前がつけられています。
来館者の皆さんには、たくさんある雪の結晶の中からお気に入りの雪の結晶を見つけて、雪の結晶分類ストラップを作っていただきました。

コース5:雪結晶のしおりを作ろう
雪の結晶は、気温や湿度など空の状態に大きく影響されて形が変わります。そのため、雪の結晶の形を見比べることで雪雲の中の気象状況を推測することができます。
来館者の皆さんには、そんな雪の結晶のお好みの形を切り抜いたしおりを作っていただきました。読書の秋に、ぜひ使ってみてください。

コース6:雪結晶の万華鏡づくり
雪の結晶にはいろいろな形がありますが、その多くは中心から6つの方向にのびた形をしています。そこで、そのような模様が見える万華鏡を、来館者の皆さんに作っていただきました。
万華鏡には、いくつか種類があります。今回の万華鏡は2枚の鏡をV字型に組み合わせ、そこへ黒い紙を合わせて三角柱を作ります。すると、鏡の反射によって雪の結晶のような模様が見える万華鏡ができあがります。

コース7:スマホでさつえい ゆきけっしょう
「藤野式雪結晶透過光観察台」という、便利な装置があります。雪の結晶を観察したり、写真を撮影したりすることができる装置です。
今回はその装置の改良型を使って、来館者の皆さんに雪の結晶の観察したり、スマートフォンで雪の結晶を撮影したりしていただきました。

コース8:雪の上の小さな生き物をのぞいてみよう
冷たい雪の中にも小さな生き物が住んでいたり、ほかのところから飛んできた微生物が含まれていたりします。
雪の中にはどんな生き物が住んでいるのか、どんな微生物が含まれているのか、来館者の皆さんに顕微鏡を使って観察していただきました。

コース9:雪の結晶の成長
ドライアイスやペットボトルを使って、雪の結晶が成長する様子を観察できる平松式人工雪発生装置を来館者の皆さんに体験していただきました。
雪の結晶は、樹枝状結晶や針状結晶など、結晶の形によって成長のしかたが異なります。そのため、異なるパターンの成長の様子も観察していただきました。
また、今回はダイヤモンドダストも観察していただきました。

コース10:氷の冷熱で発電?ペルチェ素子を使った実験
ペルチェ素子は、温かいものと冷たいもので挟むと、その温度差で電気を生み出すことができる素材です。
今回は、手のひらと氷でこのペルチェ素子を挟み、人の体温(約36度)と氷の温度(約0度)の温度差を利用して発電する実験に挑戦していただきました。
氷の上のペルチェ素子に手をのせると発電してプロペラが回る様子を、来館者の皆さんは楽しそうに観察していました。

コース11:ゆきのおもさはどれくらい?
雪が降り積もるとき、気温や湿度などの気象条件によって雪の性質が変わります。また、雪が降り積もったあとでも、その後の気温などの違いにより、雪質が変わります。
こうした雪質は、おおまかに「新雪」「しまり雪」「ざらめ雪」「しもざらめ雪」の4種類に分類されていて、来館者の皆さんには、4種類の雪質の雪で作られた雪だるまと同じ大きさ・重さの雪だるまのぬいぐるみを抱いてもらい、その重さの違いを体験していただきました。

コース12:目指せ!雪かき名人 雪かきバスケット
雪かきは、ちょっとコツを覚えると、安全で手際よくすることができます。この「雪かきバスケット」は、そんな雪かきのコツを楽しく学べる的当てゲームです。
来館者の皆さんは、床に置かれた雪に見立てた砂袋を、ひな壇状に置かれた点数付きのバケツに向かって、スコップを使って一生懸命にすくい上げていました。
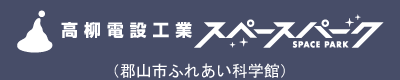





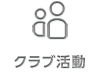
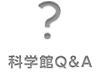
 HOME
HOME




