2025年10月19日(日)
今回は、大越先生、安田先生が担当です。テーマは「キッチンの科学 色実験を楽しもう!」です。

最初に、大越先生から次のような説明がありました。「物」と「物体」は、同じようなものであり、「物体」と「物質」は、違いがある。例えば、「物体」としてのスプーンがあったとして、それを作る材料となるステンレス・プラスチック・木を「物質」という。つまり、見た目や使う目的に着目した時には「物体」といい、「物」の材料に着目した時は「物質」と理解してほしい。
皆さんのキッチンには、たくさんの「物質」があり、今回は、固形として、食塩・バタフライピーティー(紫キャベツ)、液体として、水溶液(石鹸水他5種類)を使っていきます。

次に、水溶液を分類するための液を作りました。バタフライピーティーにお湯を入れ、かき混ぜると紫色のお茶ができました。ここでは、これが分類に役立つことはまだわかりません。
その後、6種類の試験管の水溶液を観察し、色はあるか、透明かどうか、においはあるかなど一つ一つ持ち上げてじっくり見たり、鼻を近づけてにおいをかいだり、同じ班の友達と相談しながら分類していました。中には、においがするから「アンモニア水」かもなど、水溶液の種類にまで気を配っていたクラブ員もいました。

見た目と臭いで分類した水溶液に、バタフライピーティーの液を6種類の試験管に入れていきます。それぞれの試験管の水溶液の色が変わるたびに、「わー、すごい。」「きれいな色。」等の歓声があがりました。
最後に、先生から、赤は酸性、青はアルカリ性、その間は中性になることを教えてもらいました。感想には、「この実験は楽しかった。」「酸性やアルカリ性があることが分かった。」「家にあるものでも試験紙を使って調べてみたい。」など、それぞれが実験wを通しで得られるものがあったようです。
次回の活動は、11月9日に日本弁理士会の出前知財授業を行います。お楽しみに!
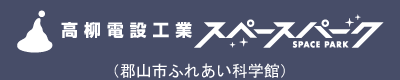





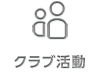
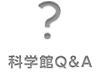
 HOME
HOME




