浮き沈みの科学 2025年10月25日(土)

今回は、ものの浮き沈みをテーマに進めました。私たちの身の回りにある様々なもの、例えば、木、鉄、プラスチックなどを使って水やアルコールに浮くかどうかの実験をしました。その中でものが浮くということはどういうことなのかを探っていきました。これらの実験結果から、浮くものと沈むものの違いは、同じ体積の水と比べて、重いか軽いかによることが分かりました。当初、予想したもの全体の重さは関係がないことも分かりました。さらに、鉄のように沈むものでも、形を変えて中を空洞にすると浮くことができることも分かりました。

後半は、魚の形をしたしょうゆ入れを使って、浮き沈みを利用した工作「浮沈子」を作りました。
しょうゆ入れにナットをつけ、魚の出来上がりです。魚に水を入れます。魚の浮き具合を調整して、水の入ったペットボトルに入れます。このペットボトルを握ると魚は沈み、離すと浮くのです。なぜそうなるのでしょうか。ペットボトルを握るとペットボトルの中の水が押されます。そして魚の中の空気も押され縮みます。空気が縮むと浮力が小さくなるので魚が沈みます。手を離すと元の浮力にもどり浮き上がるという仕組みです。浮き沈みのメカニズムを学んだ活動でした。
次回は12月20日(土)に「音のひみつ」を行います。お楽しみに!
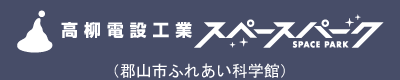





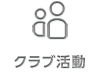
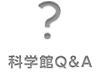
 HOME
HOME




